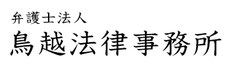債権譲渡(担保)・債権回収に関して押さえておきたい裁判例
裁判例13:将来債権の譲渡担保契約と国税徴収法24条6項(現8項)
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、譲渡の目的とされる債権が特定されている限り、原則として有効なものである(最高裁平成11年1月29日判決)。また、 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された場合には、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない限り、譲渡担保の目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されているのであり、この場合において、譲渡担保の目的とされた債権が将来発生したときには、譲渡担保権者は、譲渡担保設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができるものである。そして、前記の場合において、譲渡担保契約に係る債権の譲渡については、指名債権譲渡の対抗要件の方法により第三者に対する対抗要件を具備することができるのである(最高裁平成13年11月22日)。
以上のような将来発生すべき債権に係る譲渡担保権者の法的地位にかんがみれば、国税徴収法24条6項(現8項)の解釈においては、国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的として、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され、その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には、譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても、当該債権は「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。
(解説)
原判決は、将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結された場合、目的債権が現実に発生した時に譲渡担保権者に移転するという説(債権発生時説)に立ったうえで、 本件国税の法定納期限等の後に発生した本件債権は「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに当たらないとした。本判決は、債権の移転時期についての民法上の論点に関する判断を留保し、国税徴収法の解釈問題として判示した。